祇園・花見小路の南端、建仁寺の向かいの小道を入った先にたつ、建仁寺南の家。
2021年11月に全面リノベーション済みの京町家です。
建仁寺南の家 物件掲載ページはこちら
京都を代表する名所に囲まれた立地が特徴です。
建仁寺の家から、ふらりと歩いて行ける名所をご紹介します。

■初回オープンハウス開催
11/20(土)・21(日) 1400-16:00
・ご予約は不要です
・恐れいりますが初回オープンハウス前のご案内は承っておりません
・駐車場はございません。公共交通機関や近隣のコインパーキングをご利用ください
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のためのお願い※
・マスクをご着用ください
・入口にてアルコールによる手指消毒のご協力をお願いします
・現地は換気のため常時窓や扉を開放します
・発熱など体調が優れない方はご来場をお控えください
・スタッフはマスクを着用してご対応いたします
お手数をおかけしますが、皆様のご健康とご安全のため、ご協力をお願いいたします。

祇園、建仁寺、八坂神社、高台寺など、京都屈指の名所に囲まれた、建仁寺南の家。
季節を問わず国内外の観光客でにぎわう名所へ、ふらりと歩いて行けるのは、この町家ならでは。
また、京阪電鉄の祇園四条駅、阪急電鉄の京都河原町駅が徒歩圏内にあり、交通アクセスも良好。市内中心部の利便性と、京都の風情が共存する立地です。
写真は、祇園の南を東西にはしる八坂通。東には祇園・東山界隈の象徴、八坂の塔(法観寺五重塔)をのぞみます。

八坂通のは、東大路通より東は石畳敷になっています。
観光シーズンの日中は非常に多くの人でにぎわいますが、朝は比較的人通りも少なく、静かな時間が流れています。
石畳沿には「%」のロゴで有名なコーヒー店、アラビカ京都東山があります。朝の散歩がてら、コーヒーを飲みに気軽に立ち寄れるのも、この町家の魅力です。

 建仁寺の境内を歩いて北門を出ると、花見小路に着きます。
建仁寺の境内を歩いて北門を出ると、花見小路に着きます。
石畳の通りの両側にお茶屋や割烹が軒を連ね、美しい景観を形成しています。夜になると格子からほのかな光が漏れ、日中とは異なる趣を楽しむことができます。
花見小路沿いにある祇園甲部歌舞練場の弥栄会館は、保存改修に加え新棟を建築し、2025年に帝国ホテルとして開業予定。今後ますます注目を集めるエリアです。
※現在は水道管工事のため一時的にアスファルトになっています。2022年に石畳を復旧予定です。
花見小路を北へ行くと、京都の中心部のメインストリート、四条通に出られます。四条通を西へ行くと京都一の繁華街である四条河原町、東へ行くと八坂神社があります。

四条通の東端に位置する八坂神社。京都三大祭りのひとつ、祇園祭は八坂神社の神事です。
隣接する円山公園は、明治19年開園という、京都市内で最も古い歴史を持つ公園です。祇園枝垂れ桜や、七代目小川治兵衛により作庭された美しい庭園を鑑賞することができます。

八坂神社から円山公園内を東へ歩くと、ひときわ存在感を放つ洋館が見えてきます。
長楽館というこの洋館は、明治42年に実業家の村井吉兵衛により建築され、国内外の来賓をもてなす迎賓館として使われていました(。
建物内部には、日本、中国、イギリス、フランス、アメリカなど、世界の様々な建築様式で造られた豪華絢爛な部屋があり、貴重な調度品が飾られ、まるで美術館のような空間です。現在はレストラン&カフェ、宿泊施設となっています。
円山公園の散歩途中に、お茶をしに立ち寄ってはいかがでしょうか。

 長楽館のすぐ東には円山公園から南へと続く石畳の道があります。ねねの道と呼ばれるこの道は、豊臣秀吉の正妻・ねね(北政所)が晩年この地で暮らしたことが名の由来となっています。
長楽館のすぐ東には円山公園から南へと続く石畳の道があります。ねねの道と呼ばれるこの道は、豊臣秀吉の正妻・ねね(北政所)が晩年この地で暮らしたことが名の由来となっています。
道沿いには秀吉の菩提を弔うためにねねが建立した高台寺、ねねが余生を過ごした圓徳院、町家建築などが軒を連ね、風情ある街並みが続きます。上の写真はねねの道と八坂の塔を見て。下の写真は高台寺の参道。

松原通を西へ歩くと鴨川へ着きます。鴨川沿いでは毎年初夏になると、京都の夏の風物詩、川床が始まります。
京都を代表する名所まで気軽に歩いていける、建仁寺南の家。
11/20(土)・21(日) 14:00-16:00
初のオープンハウス ご来場をお待ちしております。



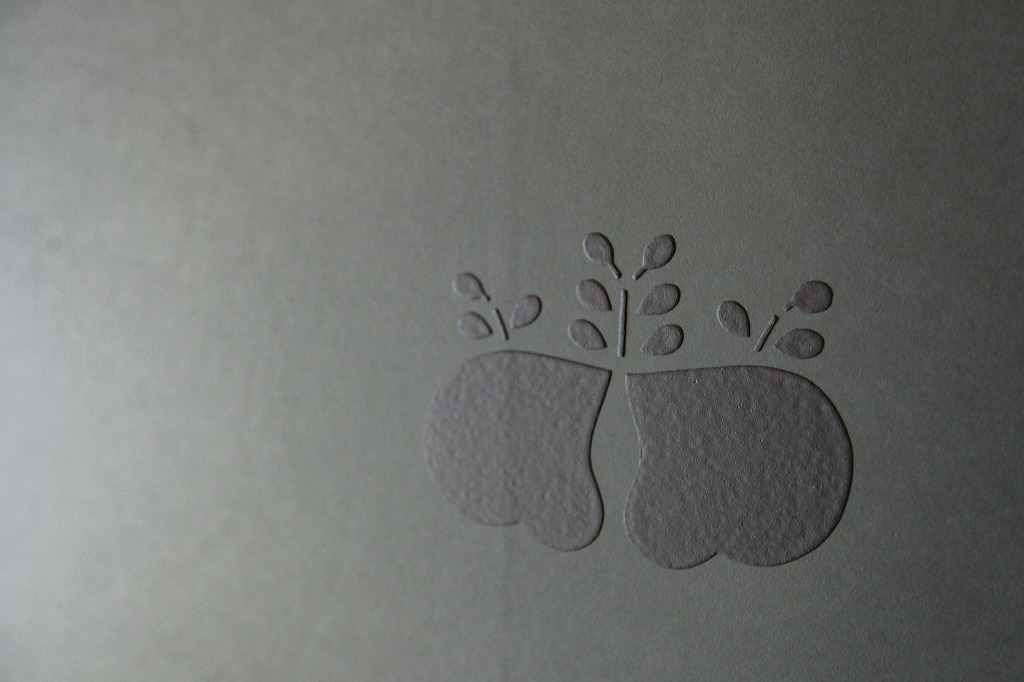








 建仁寺の境内を歩いて北門を出ると、花見小路に着きます。
建仁寺の境内を歩いて北門を出ると、花見小路に着きます。


 長楽館のすぐ東には円山公園から南へと続く石畳の道があります。ねねの道と呼ばれるこの道は、豊臣秀吉の正妻・ねね(北政所)が晩年この地で暮らしたことが名の由来となっています。
長楽館のすぐ東には円山公園から南へと続く石畳の道があります。ねねの道と呼ばれるこの道は、豊臣秀吉の正妻・ねね(北政所)が晩年この地で暮らしたことが名の由来となっています。
 玄関を見て。三和土調の土間と左官の塗り壁が暖かみを醸しています。
玄関を見て。三和土調の土間と左官の塗り壁が暖かみを醸しています。 靴箱の横はトイレの入口です。入口の建具は、リノベーションにより新たに造作したものです。
靴箱の横はトイレの入口です。入口の建具は、リノベーションにより新たに造作したものです。

 庭塀は綾目張り(菖蒲張り)という施工法で仕上げています。
庭塀は綾目張り(菖蒲張り)という施工法で仕上げています。
 2階の洋室。勾配天井で梁を現し、明るく開放感のある空間にしています。照明は、開放感を損なわないよう、小さな電球型のペンダントとスポットを選んでいます。
2階の洋室。勾配天井で梁を現し、明るく開放感のある空間にしています。照明は、開放感を損なわないよう、小さな電球型のペンダントとスポットを選んでいます。








